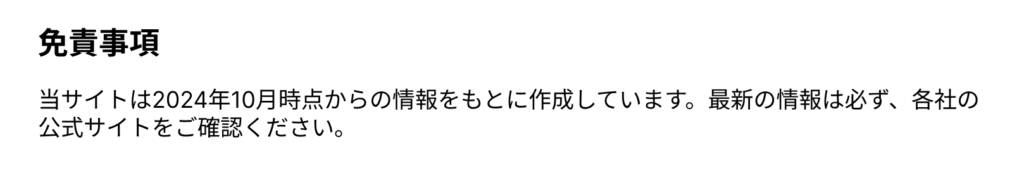「住宅ローンが残っている家はどうすればいい?」
「離婚した場合、家の財産分与はどうなるの?」
離婚時に揉める原因のひとつが不動産の財産分与です。財産分与で家をスムーズに処理するには、知識を身につけることが重要です。
そこで本記事では、離婚時に家を財産分与する際の基礎知識と方法を解説します。あわせて、不動産売却におすすめの不動産会社も紹介するため、最後までご覧ください。
さらに、以下の記事では宮城県でおすすめの不動産会社を3社紹介しています。是非参考にしてください。
離婚時に家を財産分与する際に知っておきたい基礎知識
離婚時に家を財産分与する際に知っておきたい知識は以下のとおりです。
それぞれ解説するため、ここで基礎知識をつけておきましょう。
対象
離婚時の財産分与の対象は、婚姻期間中に夫婦で取得した財産が基本です。給与や事業による収入、その収入で購入した不動産や預貯金、株式、保険積立金などが挙げられます。つまり、婚姻期間中に購入した家は、基本的には財産分与の対象です。
ただし、以下の場合は財産分与の対象外となるため、注意しておきましょう。
- 結婚前から所有していた財産
- 相続や贈与により取得した個人財産
- 別居後の財産
財産の名義が一方の配偶者だけでも、婚姻期間中に双方の協力によって形成されたものであれば、夫婦で築き上げた財産とされ、財産分与の対象となります。
種類
離婚時の財産分与には以下の3つの種類があります。
- 清算的財産分与:婚姻している期間の間に夫婦が協力して形成した財産の公平な分配
- 扶養的財産分与:離婚後に経済的自立が難しい場合の生活保障
- 慰謝料的財産分与:離婚の原因を作った配偶者からもう一方への損害賠償
3種類の財産分与は、単独で行われることもあれば、複数を組み合わせることもあります。状況によって、どの請求が認められるかは異なり、夫婦間の話し合いや裁判所の判断により決定されます。
割合
分割割合は2分の1が基本です。ただし、夫婦の状況によっては、必ずしも2分の1になるとは限りません。
たとえば、婚姻期間が長く、専業主婦として家事や育児に貢献してきた場合、金銭的な貢献は少なくても、相応の割合が認められます。一方で、婚姻期間が短く、共同生活による財産形成がほとんどない場合には、分割割合が変動する可能性が高いでしょう。
また、浪費や借金による財産の減少、不貞行為などによる婚姻破綻への責任、離婚後の生活維持能力の差など、特殊な事情がある場合には、分割割合が変わる可能性があります。
財産分与の割合は2分の1が基本ではあるものの、状況によって異なるため、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
期間
財産分与の請求期限は、離婚が正式に成立してから2年間と法律で定められています。この2年間は、家庭裁判所に財産分与の調停を申し立てられる期間です。
ただし、離婚してから2年以上経過したあとでも、夫婦間の合意があれば財産分与できます。
離婚時に家を財産分与する2つの方法
離婚時に家を財産分与する方法は、大きく分けて2つあります。
それぞれ解説するため、参考にしてください。
1.売却して現金を分ける
家を売却して現金に変えて、夫婦で分ける方法があります。明確に現金で分配できるため、将来的なトラブルを避けられるのがメリットです。
不動産会社へ家の査定を依頼し、査定金額をもとに売り出し価格を決め、売却活動を行います。売却には数か月から1年以上かかるケースが多いため、時間に余裕を持って計画することが大切です。
売却後、ローンの残債がある場合には精算し、売却益が出た場合には諸費用を差し引いた金額を分配します。
ただし、物件の状態や市場動向により、売却できない可能性や、売却までに長期間かかる可能性があるため、注意が必要です。納得のいく価格で家を売却するためには、複数社比較したうえで、信頼できる会社へ依頼することをおすすめします。
2.一方が住み続け、もう一方は現金を受け取る
家を売却せずに、夫婦の一方が住み続け、もう一方は現金を受け取る方法もあります。
この場合、住み続ける方は、もう一方へ多額の現金を用意しなければなりません。
たとえば、家の評価額が3,000万円で、住宅ローンの残債務が2,000万円の場合、正味価値は1,000万円となります。この半分の500万円を相手方に支払うことで、財産分与が成立します。
なお、支払う現金を一括で用意できない場合には、分割払いを検討することも可能です。その際は、支払い条件や期間などを明確に決めておきましょう。
一方が住み続け、もう一方は現金を受け取る場合には、以下のケースが考えられます。
ここでは、それぞれの状況別に解説します。
債務者が住み続ける場合
夫婦の一方が住宅ローンの支払いを継続しながら家を保有し、もう一方の配偶者には金銭で清算する選択肢があります。住宅ローンが残っている場合には、債務者自身が完済する責任を持ち続けなければなりません。
しかし、財産分与の支払いが済めば、住宅ローンの返済を続けるのみとなるため、債務者が住み続ける場合の財産分与はシンプルです。
債務者ではない方が住み続ける場合
ローンを抱えていない方が住み続け、もう一方に現金で清算金を支払う方法もあります。住宅ローンが残っている場合には、基本的には住み続ける方が支払いを続けなければなりません。また、ローンの名義変更が必要になる可能性があり、金融機関の承諾が必要です。
資金がない場合には、家を売却して現金化したあと、売却後も済み続ける『リースバック』を検討しても良いでしょう。短期間でまとまった資金を得られるほか、直接買取のため、仲介手数料が発生しないことがリースバックのメリットです。
ペアローンの場合
夫婦が共同で住宅ローンを借りており、どちらか一方が家に住み続ける場合には、住宅ローンを単独で引き継ぐ形となります。
一方が住宅ローンを引き受ける場合には、改めて審査が必要になり、金融機関からの承諾を得る必要があります。
離婚時の財産分与について相談するなら家に詳しい『東海住宅』がおすすめ

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 社名 | 東海住宅株式会社 |
| 住所 | 〒981-0901 宮城県仙台市青葉区北根黒松2-30 菊田参番館1F |
| 設立 | 1971年(昭和46年)9月6日 |
| 電話番号 | 0120-152-819 |
| 公式サイト | https://www.10kai.co.jp/file/tokaisale/area/miyagi.php |
家の財産分与に悩んでいる方は、東海住宅へ相談してみるのがおすすめです。同社では、離婚にともなう不動産売却のほかにも、弁護士や税理士などの専門家と連携しながら、財産分与全般の総合的なサポートを行ってくれます。
創業してから50年を超える歴史と実績がある同社は、本社を千葉県に置き、千葉・北関東・仙台エリアに20を超える事業所を展開しています。
地元に精通したスタッフがお客様ひとりひとりに対し、親身になって相談に乗ってくれるため、スムーズな売却を目指してくれるでしょう。
デリケートな問題となる離婚にともなう不動産売却は、プライバシーを配慮したうえで、さまざまな要望に柔軟に対応してくれます。情報の取り扱いに細心の注意を払いながら、豊富な経験をもとに提案を行ってくれるため、一度東海住宅へ相談してみるのがおすすめです。
また、以下の記事で東海住宅株式会社の評判や特徴も解説しているので、是非参考にしてください。
まとめ
本記事では離婚時の家の財産分与について解説しました。婚姻関係中の財産は2分の1を分割するのが一般的です。ただし、状況によって、財産分与の割合が異なる可能性があるため、夫婦間で解決しない場合には弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。
また、家を売却して現金を分割するか、一方が住み続けるかによって、財産分与の方法が異なります。
東海住宅では、離婚にともなう不動産売却を弁護士や税理士などの専門家とともにサポートしてくれるほか、リースバックにも対応しているため、一度相談してみてください。